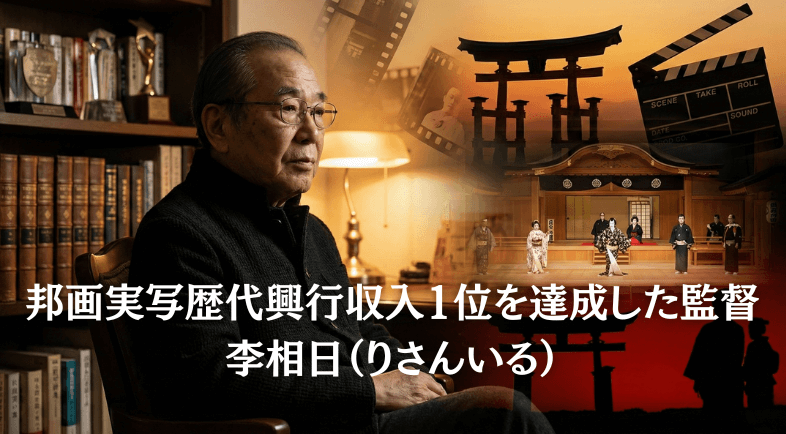邦画実写歴代興行収入1位を達成した監督・李相日は、在日朝鮮人三世として差別やアイデンティティの葛藤を抱えながら、人間の本質を描く重厚な作品群で日本映画界の頂点に立った。
2025年の『国宝』は181億円を超え、22年ぶりに邦画実写記録を更新。カンヌ国際映画祭監督週間では6分間のスタンディングオベーションを受け、東京国際映画祭では黒澤明賞を受賞した。1974年新潟生まれの李監督は、日本映画学校の卒業制作『青〜chong〜』でぴあフィルムフェスティバル史上初の4部門独占という鮮烈なデビューを果たし、『フラガール』『悪人』で2度のキネマ旬報1位を獲得。吉田修一原作作品との三度のタッグは、いずれも高い評価を得ている。
新潟から横浜へ、朝鮮学校で育んだ原風景
李相日(り・さんいる/イ・サンイル)は1974年1月6日、新潟県新潟市に生まれた。父親は新潟朝鮮初中級学校の教師であり、4歳のとき一家は横浜へ転居する。その後、小学校から高校まで横浜の朝鮮学校(神奈川朝鮮中高級学校)に通い、高校3年に進級するまでは野球部に所属していた。
大学は神奈川大学経済学部に進学したが、卒業間際にアルバイトでVシネマの製作現場に参加したことが人生の転機となった。プロデューサーの李鳳宇(シネカノン代表)の紹介で映画の現場を経験し、卒業後に日本映画学校(現・日本映画大学)へ入学を決意する。この学校は今村昌平監督が創設した教育機関であり、後に李監督が最も影響を受けた監督の一人として今村の名を挙げることになる。
卒業制作で史上初の4冠、鮮烈すぎるデビュー
1999年、日本映画学校の卒業制作として監督した『青〜chong〜』が、第22回ぴあフィルムフェスティバル(PFF)でグランプリを含む史上初の4部門独占という快挙を達成する。タイトルの「青」は日本語で「若さ」を意味し、同時に韓国語読み「chong(チョン)」は日本で朝鮮人に対する蔑称でもある。この二重の意味を込めた自伝的作品は、在日コリアン高校生のアイデンティティと葛藤を描き、ロッテルダム国際映画祭、釜山国際映画祭にも招待された。
2002年にはPFFスカラシップ作品『BORDER LINE』で劇場長編デビューを果たし、第8回新藤兼人賞金賞を受賞。バスジャック事件をきっかけに出会った5人の人々の「罪を知り、罰を受け、希望を感じるまで」を描いたこの作品が、後のキャリアを大きく開く。
『フラガール』で確立した社会派ヒューマンドラマの旗手
『BORDER LINE』を観たプロデューサーの目に留まり、2004年に村上龍原作・宮藤官九郎脚本の『69 sixty nine』でメジャー初作品を監督。続く2005年のオリジナル脚本『スクラップ・ヘブン』を経て、2006年の『フラガール』が決定的な転換点となった。
福島県いわき市の常磐炭鉱を舞台に、閉山危機の町で「常磐ハワイアンセンター」誕生の実話を描いたこの作品は、国内映画賞を総なめにする。第30回日本アカデミー賞で最優秀作品賞・最優秀監督賞・最優秀脚本賞の三冠、第80回キネマ旬報ベスト・テン1位、第49回ブルーリボン賞作品賞、文化庁芸術選奨新人賞を受賞し、米アカデミー外国語映画部門日本代表にも選出された。
主要フィルモグラフィーと評価
| 公開年 | 作品名 | 原作 | 主要キャスト | 興行収入 | 主な受賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 青〜chong〜 | オリジナル | − | − | PFF4部門独占 |
| 2002 | BORDER LINE | オリジナル | 沢木哲 | − | 新藤兼人賞金賞 |
| 2004 | 69 sixty nine | 村上龍 | 妻夫木聡、安藤政信 | − | − |
| 2005 | スクラップ・ヘブン | オリジナル | 加瀬亮、オダギリジョー | − | − |
| 2006 | フラガール | 実話 | 松雪泰子、蒼井優 | − | 日本アカデミー賞3冠、キネ旬1位 |
| 2010 | 悪人 | 吉田修一 | 妻夫木聡、深津絵里 | 約20億円 | モントリオール最優秀女優賞、キネ旬1位 |
| 2013 | 許されざる者 | C.イーストウッド | 渡辺謙、柄本明 | − | イーストウッドから絶賛コメント |
| 2016 | 怒り | 吉田修一 | 渡辺謙、妻夫木聡 | 約16億円 | 日本アカデミー賞11部門ノミネート |
| 2022 | 流浪の月 | 凪良ゆう | 広瀬すず、松坂桃李 | − | 日刊スポーツ映画大賞監督賞 |
| 2025 | 国宝 | 吉田修一 | 吉沢亮、横浜流星 | 181億円超 | 邦画実写歴代1位、黒澤明賞 |
俳優を追い込む「鬼」の演出術
李相日監督の演出は「妥協を許さない」ことで知られる。『悪人』に出演した樹木希林は「李監督は優しい顔してるけど、すごく粘り強い人でした」と語り、『許されざる者』の佐藤浩市は「久しぶりにキツい奴だった」と振り返る。出演者たちが口を揃えて「精神的に追い込まれる」と証言する現場から、鬼気迫る演技が生まれてきた。
『国宝』では主演の吉沢亮にクランクイン1年3ヶ月前から歌舞伎の稽古を課し、舞踊家・谷口裕和氏の下ですり足からマンツーマンで訓練させた。横浜流星も数ヶ月前から稽古を開始。李監督は「彼らの原資がなければ、このような形にはならなかった」と俳優への信頼と高い要求の両立を語る。
映像面でも妥協はない。『流浪の月』では『パラサイト 半地下の家族』のホン・ギョンピョを、『国宝』ではカンヌパルムドール受賞作『アデル、ブルーは熱い色』のソフィアン・エル・ファニを撮影監督に起用し、国際水準の映像美を追求している。
黒澤明と今村昌平に学んだ「支配する力」
李監督が尊敬する映画監督として挙げるのは、黒澤明と今村昌平の二人だ。黒澤について「上映中の2、3時間の中で観る者を完全に支配する力がある」と評し、今村については「人間の本性を見せつけられる感がある」と語る。両者に共通して「ユーモアのセンスに長けている」点も高く評価している。
2025年の東京国際映画祭で黒澤明賞を受賞した際、李監督は「歌舞伎で言う最も大きな名跡に、アウトサイダーのような僕が向かっていく。その怖さと重責を感じています」と述べ、巨匠の名を冠した賞への畏敬の念を示した。
いい映画の条件について李監督は「気が付かせてくれる作品」だと定義する。観客に何かを「気づかせる」ことこそが映画の使命であり、そのために「悪魔と取り引きしてでも才能がほしい」という創作への執念を公言している。
吉田修一との運命的タッグ、三度の協働
李相日監督と芥川賞作家・吉田修一のコラボレーションは、日本映画界で最も成功した監督×原作者タッグの一つとなっている。
『悪人』(2010年)は、出会い系サイトで知り合った女性を殺害した青年と、彼と刹那的な愛に落ちる孤独な女性の逃避行を描く。「真の悪人とは誰か」という問いを突きつけたこの作品は、第34回モントリオール世界映画祭で深津絵里が最優秀女優賞(日本人27年ぶり)を受賞、キネマ旬報1位、日本アカデミー賞13部門15賞という快挙を達成した。李監督と吉田が共同で脚本を執筆し、音楽は久石譲が担当した。
『怒り』(2016年)では、八王子の殺人事件を軸に、千葉・東京・沖縄に現れた素性不明の男たちをめぐる群像ミステリーを展開。渡辺謙、妻夫木聡、松山ケンイチ、森山未來、綾野剛、広瀬すず、宮崎あおいというオールスターキャストを率い、「この人を信じていいのか」という人間の信頼と疑念を描いた。音楽は坂本龍一が手がけ、日本アカデミー賞最多11部門ノミネートを記録した。
李監督は「疑いや憤りの先にあるのは肯定、そして慈しみと希望」と語り、両作品に通底する人間への眼差しを明らかにしている。
『国宝』制作秘話:15年の構想が結実した奇跡
2025年公開の『国宝』は、構想から完成まで15年以上を要した李監督のライフワークである。
企画の発端は『悪人』完成後の2010年代初頭に遡る。李監督は30代半ばで伝統芸能、特に歌舞伎の女形に強い関心を抱き始めた。当初は六代目中村歌右衛門をモデルに構想したが、製作費や歌舞伎界の協力という難題に直面し一旦断念。その顛末を吉田修一に話したところ、吉田自身が3年間歌舞伎の黒衣を纏い楽屋に入る取材を経て、4年の歳月をかけて原作小説を書き上げた。
李監督がこの題材に惹かれた理由について、「歌舞伎を鑑賞するときは立役に目が行きがちだが、映画にするとなった時に光を当てたいのは女形だった。なぜ女形というものが成り立ち、存在してきたのか」と語る。上海国際映画祭では、学生時代にチェン・カイコー監督『さらば、わが愛/覇王別姫』を観た衝撃から「いつかこんな映画を撮ってみたい」という想いを持ち続けていたことを告白した。
キャスティングについて李監督は「原作を読んだ時に、これは吉沢くんしかない。彼がやらないなら、この映画は成立しない」と断言。渡辺謙には「これを映画化するのか…かなりの覚悟がいるよ」と言われながらも、正式依頼で快諾を得た。脚本は奥寺佐渡子(『八日目の蝉』)、撮影はソフィアン・エル・ファニ、美術は種田陽平という国際的布陣で臨み、製作費は国の補助金を含め約12億円という邦画としては破格の規模となった。
歴史を塗り替えた『国宝』、社会現象への昇華
2025年6月6日に公開された『国宝』は、任侠の一門に生まれた立花喜久雄が上方歌舞伎の名門に引き取られ、「女形」として人間国宝へと上り詰める50年の壮大な一代記を175分で描く。
興行成績は驚異的だった。公開から約7ヶ月で興行収入181億円超、観客動員1286万人超を記録し、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』(173.5億円)が保持していた邦画実写歴代1位の記録を22年ぶりに更新した。4週連続で週末興収が前週を上回る異例のヒットとなり、当初約356館だった上映館は年末年始に約400館へ拡大された。
国際的評価も高い。第78回カンヌ国際映画祭「監督週間」で世界初上映され、約6分間のスタンディングオベーションを獲得。監督週間ディレクターのジュリアン・レジ氏は「作家性と商業性が良いバランスで成立する映画は近年とても珍しい」と評した。第50回トロント国際映画祭スペシャルプレゼンテーション部門でも上映され、第98回米国アカデミー賞では国際長編映画賞とメイクアップ&ヘアスタイリング賞の2部門でショートリスト入りを果たした。
社会現象としての広がりも顕著だ。2025年新語・流行語大賞トップテンに「国宝(観た)」が選出され、実際の歌舞伎公演にも若い観客が増加。トム・クルーズ主催のロサンゼルス上映会が開催され、2025年12月31日には歌舞伎座での特別上映会(全国生中継)が実施された。
結論:アウトサイダーが見せた「日本映画の可能性」
李相日監督のキャリアは、「疑い」から始まり「肯定」へと至る旅路である。在日コリアン三世として差別やアイデンティティの葛藤を経験しながら、その眼差しは常に「人間とは何か」という普遍的問いに向けられてきた。『青〜chong〜』から『国宝』まで、一貫して描かれるのは罪と赦し、信頼と裏切り、芸術への気概といったテーマであり、社会派でありながら観客の心に深く響く作品群を生み出してきた。
黒澤明賞受賞時に「アウトサイダーのような僕が」と語った李監督だが、その外部者としての視点こそが、日本社会や日本映画の本質を鮮烈に照らし出す力となっている。吉田修一との三度のタッグは、原作の本質を捉えながら映画としての独自性を追求するアプローチの成功例であり、『国宝』の歴史的記録達成は、そのすべての集大成といえる。
「この一瞬があるから生きている」と思える瞬間を観客に届けること——それが李相日監督の究極の目標であり、2025年の日本映画界における最大の達成である。